
ちょっと前に「老後のたくわえは2千万が~…」と話題になったことがありますけど、個人的にはフリーランス稼業はガンガン稼ぐことがまず第一で、ガンガン稼いで税金に「うげっ」となったあたりで節税に目が行くようになり、そして節税に励んでみたら勝手に老後の貯えができるようになっている。そんな制度設計がなされていると思っています。
このへんはまたいずれ詳細にまとめたいなーと思っているとこではありますが(自分でもすぐ忘れそうになるので)、年金の上乗せとして確定拠出年金(iDeCo)、退職金の積み立てとして小規模企業共済、一時的に資金繰りがやばくなった時のための倒産防止共済(経営セーフティ共済)。あと、ちょっと毛色が異なりますけど、平均課税制度。この4つは、自分のような業態のフリーランスなら絶対知っておいた方がいいと思うものたちです。
これらの普通に用意されている制度にのっかってフル活用するだけで、老後のたくわえなら40歳以降にはじめたとしても3千万以上が積み上がっていきますし、何よりガンガン稼いでいる人であればその年の税金が100万以上もお安くできちゃうんだから見逃せません。
なんでこれらの共済がお得なのかをさらっと言うと
上であげたiDeCoや小規模企業共済、倒産防止共済のメリットは、いずれも「掛け金が全て控除に使える」ことにあります。ざっくりわかりやすくするために復興所得税の細かい数字は無視するとして、たとえば年に課税所得金額が695万円を超える人であれば、その超えた分には最低でも住民税とあわせて30%の税金が課されることになる。900万円を超える人なら超えた分は43%が税金です。

ところが課税所得金額が795万円の人がいて、100万円をこうした共済に放り込んだとします。その100万円はまるごと控除になるから、その分の税金はかかりません。30万円の支払いは消えてなくなります(源泉徴収されていれば丸々30万円が返ってきます)。

それでいて放り込んだ100万円はそのまま将来へのたくわえになっているわけです。実質の手出しは70万円なのに、100万円の貯蓄ができちゃった。しかもさらに運用益だって出るかもしれない。超お得!
これが、こうした共済がお得とされる基本的な考え方です。
国民年金基金にも実は見逃せないメリットがあった
さて、ここまでの話で意図的に除外しているのが国民年金基金です。これも年金の上乗せとして使うもので、掛け金の全額が控除になるメリットも同じ。じゃあなんで除外していたのかというと、iDeCoがあったら正直いらないよねと思ってたからなんですよね。あっちの方が投資信託を自分で選ぶ財テクごっこもできるし、変な破綻リスクもないわけだし…と。
なんでかというと、iDeCoと国民年金基金は両者を合算して月に6万8千円が掛け金の上限金額と決まっているのです。そのためiDeCoに全力で掛け金をつっこむと枠が消えるので、国民年金基金の出番はありません。
ところがこの2つ。意外なところがちがっていました。それは控除の種類です。
iDeCoは小規模企業共済等掛金控除という形で控除を受けることになります。一方国民年金基金はというと社会保険料控除という形で控除を受けます。両者は似ているようではっきりちがっていて、確定申告の時もそれぞれ分けて金額を記載するようになっています。
この「それがどうした」と言いたくなる微妙なちがいが、実は大きく影響するのです。

小規模企業共済等掛金控除では、控除を受けるのは掛け金を納めた本人(契約者本人)しか所得控除を受けることができません。
ところがなんと社会保険料控除であれば、生計を同一にする配偶者やその他親族の分も自分の所得控除に含めることができちゃうのです。健康保険や国民年金と同じ扱いです。
つまり妻の分の年金はこっちで上乗せするようにしてやれば、その分もまるまる僕の控除になりますよ。税金もごっそり返ってきちゃいますよ。というわけなのですね。

知らなかった。ぜんぜん知らなかった。
節税にならないならわざわざこんなの入らずにNISA口座あたりで投資に回してりゃいいやとか思ってた。もっと早く知りたかった。
国民年金基金ってややこしい…
そんなわけで加入資料を取り寄せまして、どういったプランで入ればいいのかを見ています。けど…なんか細かくコースが分かれててなんだかとっても難しい。

基本的には節税分を考慮すると、15年間の支給保証さえ付けとけば払い損になることは100%ないみたいです。じゃあ、65歳~80歳にもらう分と65歳~終身(15年保証)でもらうものとを半々ぐらいにして受け取る感じにすればいいのかな。
国民年金基金のサイトに行けば、組み合わせる口数ごとにどういった年金の受け取りになるかを確認できるシミュレーションが用意されている様子。何パターンが試してみて、今月中には手続きを済ませたいと思っています。
ちなみに↑は僕の書いた税金の本です。もしこの記事が「わかりやすい」と思ってもらえたなら、こちらの本にも興味を持っていただけますと幸いです。


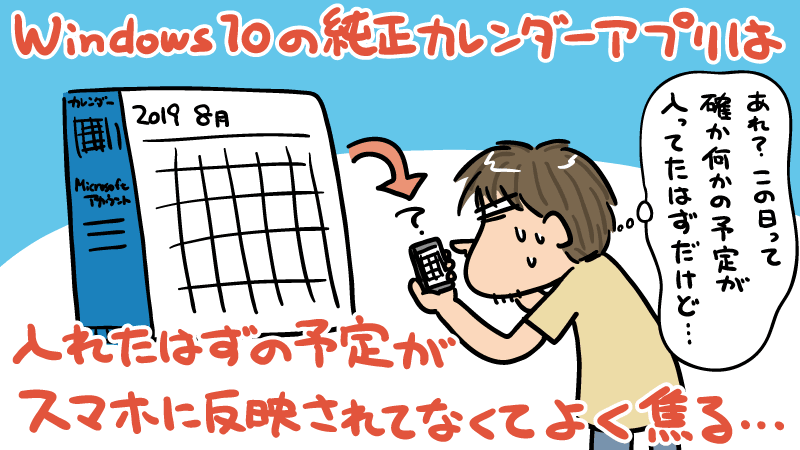

コメント